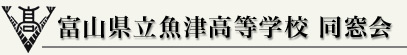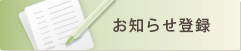特別寄稿
同窓会長 大田 弘(魚高23回生)

<今年は昭和100年>
今年は昭和という元号が始まって100年の節目の年にあたります。
凡そ300万人の日本人が亡くなった悲惨な太平洋戦争を挟んだ有史以来の“激変“の100年といえる時代でもありました。
明治以降、国際化に大きく舵を切り、ひたすら豊かさを求め働き続け、世界からは“ウサギ小屋に住む”ワーカーホリック(仕事中毒)と揶揄され、時にはJAPAN as Number Oneと褒め殺しされ今日に至っています。
そして今、国内外ともに不安定かつ不透明な時代に遭遇し、残念なことに、戦後の動乱期ですら起きなかったような凶悪かつ陰湿な犯罪が頻発しています。
世代問わず、誰しもが『こんな社会で良いのだろうか?』と戸惑いながらも、さ迷っているような気がします。
<昭和の“光と影”>
昭和の時代を良かったと懐かしむ人もいれば、苦しかった、あまり思い出したくないとい
う人もいます。飛躍的に便利で豊かになったことは多くの人が認めることですが、明るい話題も暗い話題も我々昭和世代がもたらしたものです。光と影、光(誇り)と同時に影(反省)でもあります。
我々昭和の世代の頑張り方が全て正しかったのか?“成長”と云う目標をモノやお金に重きを置きすぎたのではないか?その過程でもっと大切なものをどこかに置き去りにして来たのではないか?自分自身、我々世代への問いかけであります。
<共生(ともいき)社会は取り戻せるか?>
お互いに励まし合いながら、そして助け合いながら一生懸命に生きることで、今日の豊かさを得た“共生(ともいき)”の精神は一体何処に行ってしまったのでしょうか?
グローバル社会がもたらした光と影、経済至上主義は目先の金銭的損得に民(たみ)の関心を引き寄せてしまいました。
<籠(かご)に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋(わらじ)を作る人>
籠(かご)に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋(わらじ)を作る人という格言があります。社会がいろいろな人々の協力によって成り立っている”お陰様“を表現したものです。
例えば、籠の担ぎ手は前と後ろにいますが、相手のことを考えずに自分のペースだけでそれぞれが籠を担ぐと(進むと)籠はひっくり返ってしまいます。
また、草鞋を作ってくれている人への感謝の気持ちも忘れていけません。
籠に乗っている人は、道がぬかるんでいる時には籠から降りて一緒に籠を担ぐことが大切です。
混迷の時代ですが、昭和の作法”お陰さま“を時折、思い出して貰えば幸いです。