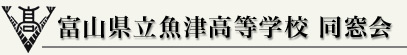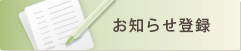令和6年度同窓会入会式 会長挨拶要旨
令和7年2月28日
同窓会長 大田 弘(魚高23回生)

皆さん、こんにちは!ご卒業、おめでとうございます。
皆さん方の関心とは少し外れるかと思いますが、今年は“昭和”という時代・元号が始まって100年、また凡そ300万人の日本人が亡くなった戦争が終わって80年という節目の年にあたります。
<昭和の“光と影”>
昭和の時代を良かったと懐かしむ人もいれば、苦しかった、あまり思い出したくないという人もいます。
便利で豊かになったことは間違いのないことですが、しかし一方で今、戦後の動乱期ですら起きなかったような悲惨・非情な犯罪、陰湿、残酷な事件を耳にすることが多くなりました。
明るい話題も暗い話題も我々昭和世代がもたらしたものです。光と影、光(誇り)と同時に影(反省)でもあります。
<昭和世代への問いかけ>
我々の頑張り方が全て正しかったのか?
“成長”と云う目標をモノやお金に重きを置きすぎたのではないか?
その過程でもっと大切なものをどこかに置き去りにして来たのではないか?自分自身、我々世代への問いかけであります。
<柿の実三つとお陰さま>
その意味を込めて、私がこれまでの人生の中で最も心に刻み込まれている言葉を皆さんに紹介します。
その事件は60年以上も前の小学生の時に起きました。
家の柿の木に“熟した実”が三つなっており、私は90歳近い祖母に柿を採って!とねだりました。
祖母はこう言いました。
「分かった。でも一つだけだよ」
私は尋ねました。「えーっ!何で一つしかくれないの?」
祖母は
「いいか?もう一つは鳥に食べさせる。そしてもう一つは地面、土に返すんだ」「ヒトはいろんなもののお蔭さまで生きているんだぞ」と
この言葉は私が大学を出て、黒部ダム”くろよん“建設に参画した憧れの会社に入って社長になった時も頭から離れませんでした。
それどころか競争社会、経済至上主義の真っただ中、社会の在り方に疑問を感じれば感じるほど、この「柿の実三つ」がますます気掛かりになりました。
祖母は家庭の事情で小学校にもほとんど通えませんでした。カタカナ、ひらがなの読み書きも出来ませんでした。そんな祖母が一体誰から人として生き方の基本、作法「お陰さま」を教わったのか?また何故?生涯その生き方を貫き通せたのか?
社会人を卒業した今も「柿の実三つとお陰さま」に如何に近づくことが出来るか?
私のラストスパートであります!

<お陰さまを忘れずに!>
皆さん、これから先、沢山の理不尽な場面に出会うでしょう。一生懸命に努力しても思うようにならない残酷な現実もあります。才能があってさほど努力することなく目標を叶える人もいるでしょう。また逆の人もいるでしょう。
その泣き笑いの時々に今、申し上げた”昭和“の言葉、「柿の三つとお陰さま」を思い出して貰えば有難いと思います。